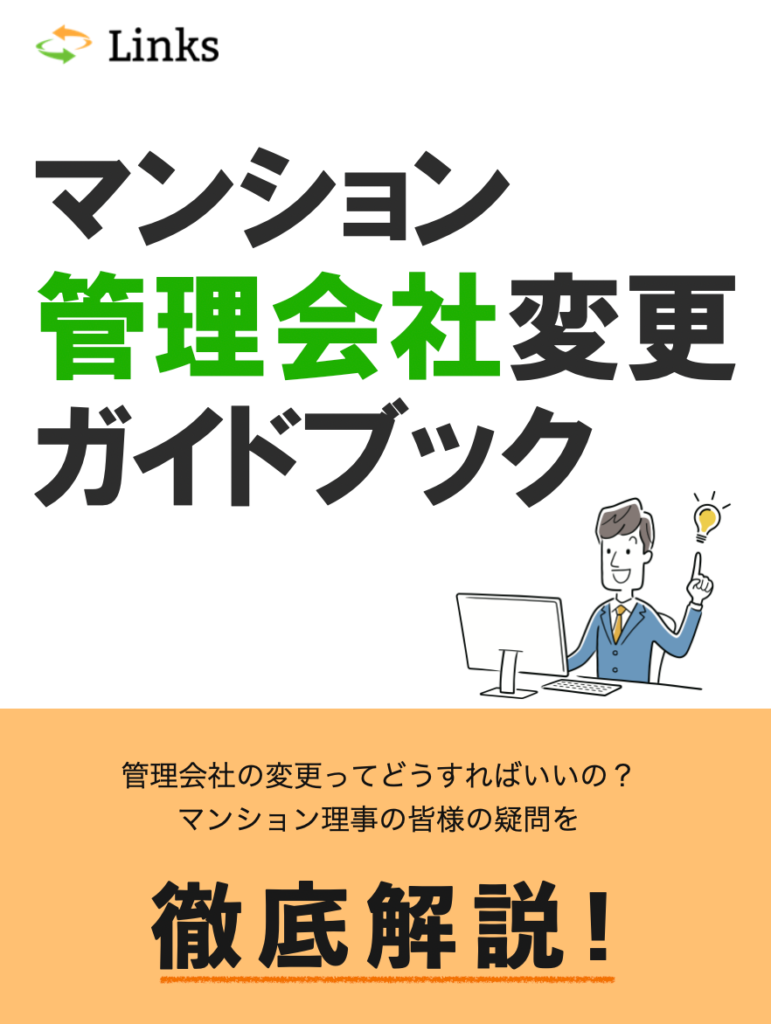値上げを言われる前に動く理事会が「契約の主導権」を握る方法とは?

2026年度の契約更新期を前に、多くのマンションで「管理委託費改定(値上げ)」の通知が見込まれています。背景には、人件費の上昇、法改正対応、電力・保険などのコスト増という業界構造の変化があります。しかし理事会として本当に注目すべきは、金額そのものではなく「値上げをどう受け止め、どう交渉するか」です。
管理会社からの説明の有無、根拠の提示、改善提案の内容によって、理事会の主導権が大きく左右されます。今回は管理会社から値上げ要請があった場合に、理事会が取り得る具体的手順と、その前提で「管理会社変更も視野に入れた判断軸」を整理します。
なぜ今、管理委託費の値上げが起きているのか
値上げが「単なるインフレ」ではなく、構造的な変化として起きている理由を理解することで、理事会としての対応の方向性が明確になります。まずはその要因を解き明かしていきます。
人件費・人材確保コストの急増
マンション管理の現場では、管理員や清掃員の高齢化・人材流出が進み、募集費用や時給の上昇が避けられなくなっています。ある管理会社の実例では、管理員1人が複数棟を兼務している状況もあり、「採算割れマンションでは委託費の引き上げを要請せざるを得ない」状況が報告されています。
理事会側としては、このような“人件費上昇が背景である”という理解をもとに、管理会社からの提示内容を精査する必要があります。

電子化・法制度対応が新たな負担に
管理会社にとって、帳簿・議事録・資料保管のデジタル化や理事会のオンライン化・電子掲示板導入など、法令改正や業界変化に対応する投資が発生しています。大手に委託している管理組合の多くは、管理会社が提供する専用システムを含めて、電子的なやり取りが多くなっているのではないでしょうか。
管理委託費の見直しを検討する際も「値上げ要請に対して、まず業務仕様を見直す」べきでしょう。 理事会としては「この電子化対応費用がどこまで契約に反映されているか」を確認することが重要です。
エネルギー・保険・資材コストの広がる影響
共用部の電気料金高騰、建物保険料の上昇、資材の値上げなどは、管理会社の“原価側”を押し上げる要因です。管理会社自身が「採算維持のために委託料見直し」を提示するケースも増えています。
これを知った理事会は、支出増の一因として納得すると同時に、「どこまでが合理的か」を見極める目を持つ必要があります。
管理会社側の撤退・採算見直し圧力
特に小規模・老朽化マンションでは、管理会社が採算確保できず「契約更新しない」あるいは「値上げを前提条件にする」姿勢が表れています。 当社に対して寄せられる多くの管理会社変更希望のケースもこれにあたります。
理事会にとっては「値上げ抵抗=契約見直し検討」の引き金になるケースです。
理事会を悩ませる「突然の値上げ通知」
理事会が直面する典型的なパターンを理解しておくことで、事前準備が可能になります。具体的にはどのようなことが行われるのか、この章で確認しておきます。
契約更新の3か月~半年前に通知が届く
管理会社の多くが、契約満了前に「次期管理委託料についてご検討ください」と通知し、理事会に短期判断を迫ります。検討や相見積もりの時間が十分に確保できずに、流れで承認せざるを得ない状況に陥る理事会が多数あります。
もちろん、管理会社側も管理組合にとって管理不在の空白期間が出来てしまうことは無責任と考え、通知の前に予め内示がなされる場合もあります。それであっても、管理組合としては慌てることとなってしまいます。

説明資料が簡素で、具体的根拠が示されない
値上げ案には「人件費・物価上昇のため」という記載が多く、明細や内訳がないことが課題視されています。管理組合側も「理由や詳細を確認すべき」であることが非常に重要です。 管理組合として、まずはこの部分こそ「交渉の入口」と捉えるべきです。
理事会/総会の意思決定時間が圧迫される
理事会開催のサイクル(月1回や隔月開催等)と通知時期のズレにより、理事会は十分な情報収集・議論・比較検討の時間を持てません。さらに、総会での説明資料準備も急ぎになりがちです。
このようなスケジュールの圧迫が、理事会の主体性を削ぎます。
契約自動更新条項が理事会の交渉余地を縮める
契約書に「自動更新」条項が含まれていると、理事会があらためて契約条件を交渉する機会が実質的に失われます。理事会はこの点を契約更新前に確認しておかないと、値上げを受け入れざるを得ない状況に陥ります。
値上げを言われた時の理事会対応
理事会が“受け身”から“主体”に変わるためのステップを解説します。
値上げ理由の文書化を求める
まず理事会が取るべきは、値上げ理由とその根拠を文書で提出するよう管理会社に求めることです。「どの業務が」「どれだけ時間・人員・単価上昇したか」を明示して貰いましょう。
当社を通じて管理会社変更に成功したある理事長のインタビューの中に、「契約書に記載すらない費目」を指摘し、それが管理会社変更の決断材料になったという事例があります。 根拠があいまいであれば、交渉の余地ありと判断できます。
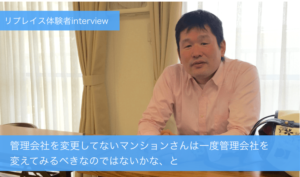
一律値上げではなく項目別・仕様別で精査する
もしも管理会社からの値上げ案が「全体5%アップ」など一律提案であれば、理事会として仕様書と契約内容をもとに「どの項目で上がるのか」を検証すべきです。また、考え方によっては「業務を減らして費用据え置きの可能性を探る」ことも考えられます。
理事会が仕様の見直し提案を行えば、値上げではなく「費用適正化」の交渉に変わります。
改善提案を要求し、付加価値を引き出す
値上げを了承するなら、その分の改善を管理会社から提示して貰いましょう。例として、「管理員配置の効率化」「“報告書のデジタル化」「巡回頻度再設計」などが挙げられます。
「改善提案や質の改善がない値上げ」の場合は、管理会社見直しの対象となってくる可能性があります。理事会としては、費用=品質向上のモデルを持つことが必要です。

他社見積を取ることで交渉力を高める
理事会が一社の提示をそのまま受け入れるのではなく、複数社から見積や提案を取得して“相場”を把握するだけでも、管理会社側の対応が変わります。当社が関与した管理組合においても、相見積もり実施が管理会社側の改善提案を引き出したという事例もありました。
理事会には予算内で最適な契約を選ぶ義務がありますので、比較検討は必須です。
理事会が「契約の主導権」を取り戻すには
理事会が真に主導権を握るためのポイントを整理します。単に値下げ交渉に強いという意味ではなく、「理事会が契約を主体的に扱える状態にする」ことが重要です。
契約書・仕様書を定期的に点検する
契約書や仕様書は、「結んだら終わり」ではなく、更新ごとに内容を読み直すべき文書です。理事会議事録に「契約内容を確認しました」と記録を残すだけでも、管理会社の意識が変わります。
このように、理事会のチェック体制を整備することが推奨されます。
説明・提案の「質」で管理会社を評価する
管理会社の比較検討において、価格だけで判断するのではなく、説明の丁寧さ、改善提案の有無、対応スピードなどを評価軸に入れるべきです。管理会社変更サインの記事でも、「価格より姿勢で選ぶ」という文言が目立ちます。
理事会が「共同運営のパートナー」として管理会社を見る視点が重要です。
理事会内で情報を共有し属人化を防ぐ
契約を理事長だけで扱う状態では、理事会としての交渉力が弱まります。契約書・見積書を理事会全員で共有し、「どこでどれだけ上がるか」を共有し、具体的に議論することで、理事会としての一貫性を保てます。
このような視点では、理事会の体制整備が重要であると言えます。

検討開始を契約満了の3か月前からに設定
契約満了の直前では比較検討の時間が足りません。理事会としては、更新期の3か月以上前から「値上げ案の有無」「他社見積の取得」「改善提案の確認」を始めるべきです。
さらに、管理会社変更を視野に入れるのであれば、この検討タイミングの早期着手が不可欠です。

まとめ ― 値上げの波を「理事会改革」のチャンスに
改定は避けられない事情もありますが、理事会が値上げに振り回されるのではなく、契約そのものを見直す機会として捉えることが重要です。提示された金額に先んじて、「根拠」「仕様」「改善提案」を問い、理事会として主体的に動くことが重要です。