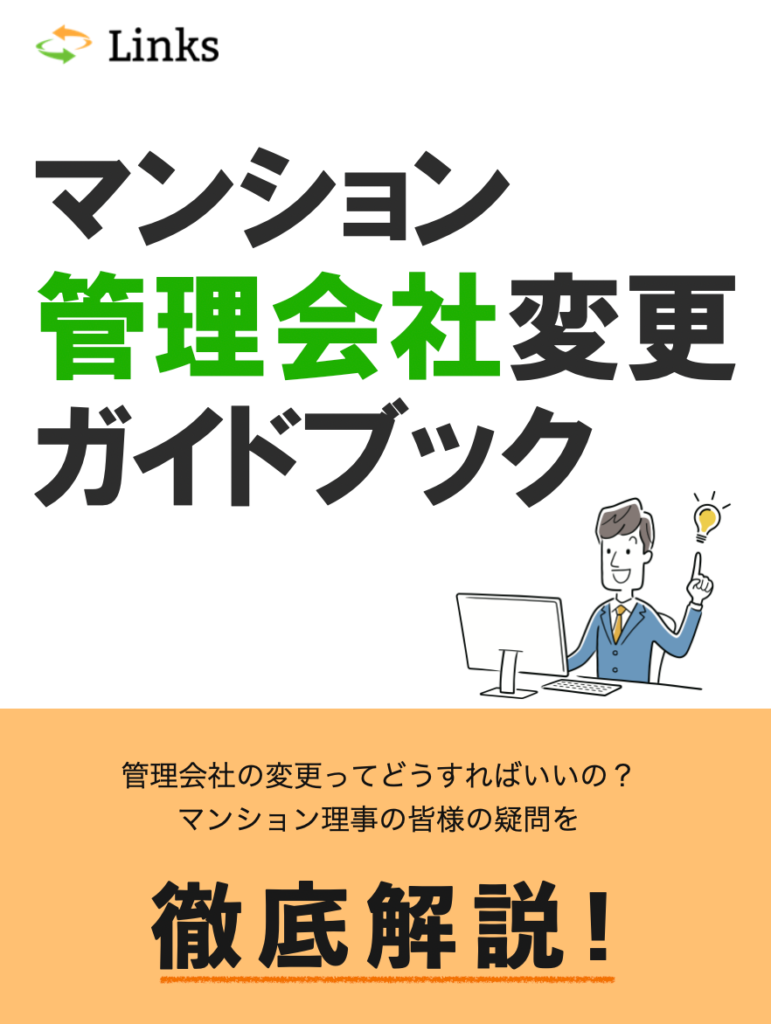管理会社変更を希望する管理組合が増加中 理事会が取るべき対応とは

分譲マンションの世界では、「管理会社変更」が他人事ではなくなってきています。国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、管理組合の69.1%が分譲時からの管理会社に管理を委託している一方、24.5%の管理組合が過去に管理会社を変更したと報告されています。
さらに言えば、昭和59年までに完成した築40年以上のマンションでは、半数以上が分譲時の管理会社からなんらかの変更を行ったという傾向も出ています。
つまり最近であっても4分の1近く、そして高経年においては半数以上のマンションが管理会社を入れ替えており、管理会社変更は珍しいことではなくなりました。背景には、管理会社側の人員不足や採算悪化、管理組合側の不満の高まりなど複数の要因があります。
このような環境ではあるものの、管理組合が一方的に変更を希望すれば新たな管理会社が受託してくれるという、引く手数多な状況から変わってきつつあります。
最近の動向を踏まえながら、管理組合や理事会が取るべき対応を紹介します。

管理組合と管理会社のいまの関係性と変化
管理組合と管理会社の間の関係性は、現状どのような傾向にあるのでしょうか。最近当社に寄せられる相談も踏まえながら紹介します。
管理会社から「次の契約は更新できない」と告げられるケース
最近増えているのが、管理会社側から契約更新を拒否されるケースです。
管理会社は営業利益を確保するために管理棟数を調整しており、人材不足や採算の悪化が進むと、採算性の低いマンションの管理を打ち切る動きが出ています。管理業界ではフロント担当者や管理員が慢性的に不足し、管理会社によっては1人が10棟以上のマンションを担当することもあります。これにより、フロント担当者の業務に負荷がかかるとともに、想定人員を確保できない期間が続くと「管理棟数を見直す」必要が生じます。
さらに、小規模で採算の低いマンションや老朽化が進み修繕も控えめな物件は、管理会社としてもその業務を行う機会が減る事から利益率が低く、管理会社が契約終了を選択する場合もあります。その結果、管理組合は突然「来年の契約は更新しない」と告げられ、慌てて新たな管理会社を探す相談が当社にも急増している傾向です。

採算性の低い管理組合契約を見直す管理会社の動き
管理会社にとって採算が合わないマンションでは、委託料の値上げを要請するか、契約解除を選ぶケースが目立ちます。小規模マンションは業務も少な目であることから管理員派遣時間が短く、管理委託料も少ないため利益率が低く、大規模マンションが優先されがちです。
そして、老朽化が進んだマンションでは漏水や緊急対応が多く、担当者の負担が大きくなるため、採算面から契約を続けたくないという声も出始めているようです。さらに、最低賃金や人材採用コストが年々上昇しており、管理員や清掃員の時給の上昇が経営を圧迫してしまいます。
このため、委託費増額に応じない管理組合とは、契約更新できない辛い事情が管理会社側にもあるのです。
他社が手放す管理組合を“おこぼれ”として受託する動き
一方で、他社が契約を打ち切った管理組合を「おこぼれ案件」として取り込む管理会社も出ています。
大手管理会社が採算性の低さから撤退したマンションでも、地場の中小業者やリプレイス専門の管理会社が受託することで、これまで同様に新しいビジネスチャンスが生まれていることも事実です。
管理会社選びの際は、複数社から提案を受けて比較することが非常に重要です。
管理組合からの相談が増えている主な要因
次に、管理組合から当社に相談が増えている主要因として考えられることを紹介します。
突然の契約終了で代替管理会社を探さざるを得ない
管理会社から契約更新を拒否された場合、管理組合は短期間で新しい管理会社を見つけなければなりません。
契約終了通知は通常3か月前に行われることが多く、理事会は即座に臨時会合を開いて対応方針を決める必要があります。次の管理会社を見つけるまでの時間も限られるため、複数社から見積もりを取り、条件や費用だけでなく担当者との相性や提案力を比較することが非常に重要です。
管理委託費の値上げ要請をきっかけに他社を検討する
人件費や採用費の高騰に伴い、管理会社が委託費の増額を要請するケースが増えています。
管理員派遣費は「管理員の時給×勤務時間+法定福利費」が大きな割合を占めており、最低賃金の上昇によって管理会社の費用負担は増加しています。
そして、値上げに納得できない管理組合は、サービス内容や費用を見直し、他社への変更を検討するようになりました。実際、管理会社に対する不満として「不要不急の工事提案」「高額な工事費」「高額な委託費」が挙げられており、これが管理会社変更の引き金となっているとも言われています。当社や筆者が関わった管理組合でも、同様の相談を受けることが増えています。
大規模修繕を前に現行管理会社への不安が高まる
築年数の経過したマンションでは、大規模修繕工事が迫る中で現在の管理会社の力量に不安を抱く管理組合もあります。
長期修繕計画や資金計画の提案が不十分だったり、過去の工事でトラブルがあった場合、理事会は早めに他社へのリプレイスを検討します。マンション管理適正評価制度などの導入により、管理の質が星数やコメントで可視化されるようになり、誰でも閲覧可能な状況にもなっています。その結果、評価が低いと区分所有者から管理会社に対する不満が高まることも考えられます。
こうした不安は、当社への問い合わせを含めて、管理会社変更としての需要にも表れています。

管理組合が今からできる現実的な対策
これらの傾向から、管理組合としてこれから対応できる現実的な対策について紹介します。
現在の管理会社に改善を求め、協議の余地を探る
契約終了の通知を受けていない場合でも、現行の管理会社に対して課題を整理し、改善を要望することが重要です。更新拒否の主因には人材不足や採算悪化、老朽化などがありますが、管理組合の対応次第でリスクを軽減できる部分もあります。
例えば長期修繕計画や資金計画を早めに見直し、余裕を持って将来必要な工事に備えること、管理会社への過剰な要求やカスタマーハラスメントを組合員が行わないようにするために役員や理事会が配慮すること、管理組合独自の会計処理や管理方法を一般的な方式に是正することなどが挙げられます。
管理会社が続けやすい環境を整えれば、更新拒否のリスクを下げられます。
いざという時に備えて候補会社の情報を水面下で集める
突然の契約終了に備え、現行の契約が継続している間から候補となる管理会社の情報収集を始めましょう。マンション管理士や当社の「管理会社マッチ」のような専門サイトを活用して、料金体系やサービス範囲、実績などを把握しておくと、急な対応が必要になった時に慌てずに済みます。
冒頭で紹介した通り、国土交通省の調査では、平均でも管理組合の24.5%が実際に分譲時からの管理会社を変更しているため、自分たちも対象になる可能性があると意識しておくことが大切です。

契約終了を突きつけられたら迅速に代替会社を選定する
実際に契約終了を告げられた場合は、時間との勝負になります。
通知を受けたらすぐに理事会を開催し、引き継ぎ業務の整理や暫定契約の可否を確認します。その上で、複数の管理会社から相見積もりを取り、費用やサービス内容だけでなく担当者の対応力を比較検討します。
必要に応じて、短期間の暫定契約を現行の管理会社に打診し、管理業務が途切れないようにすることも考えましょう。自主管理へ移行する選択肢もありますが、徴収や会計業務が滞ると管理不全に陥る危険が高いので、慎重に判断します。
管理会社変更は「他人事」ではなく、理事会が主体的に備える時代へ
管理会社変更の動きは今後も続くと見込まれます。管理業界の人材不足や高経年マンションの増加、最低賃金の上昇など構造的な問題が背景にあり、管理会社変更の検討は理事会にとって避けて通れないテーマです。
国土交通省の調査でもあったように、多くの管理組合が管理会社を変えており、値上げ要請やサービスへの不満が増える中で、管理会社変更に関心を寄せる区分所有者も増えています。
理事会は管理組合の主体性を取り戻し、管理会社との関係をビジネスとしての対等な契約と捉え、計画的な資金管理と情報収集でリスクに備えることが重要です。
そして、管理会社に「おまかせ」で済ませられる時代は終わりつつあります。理事会が中心となって、早めの準備と主体的な対応をすることが、マンションの資産価値と居住者の安心を守る鍵となるでしょう。